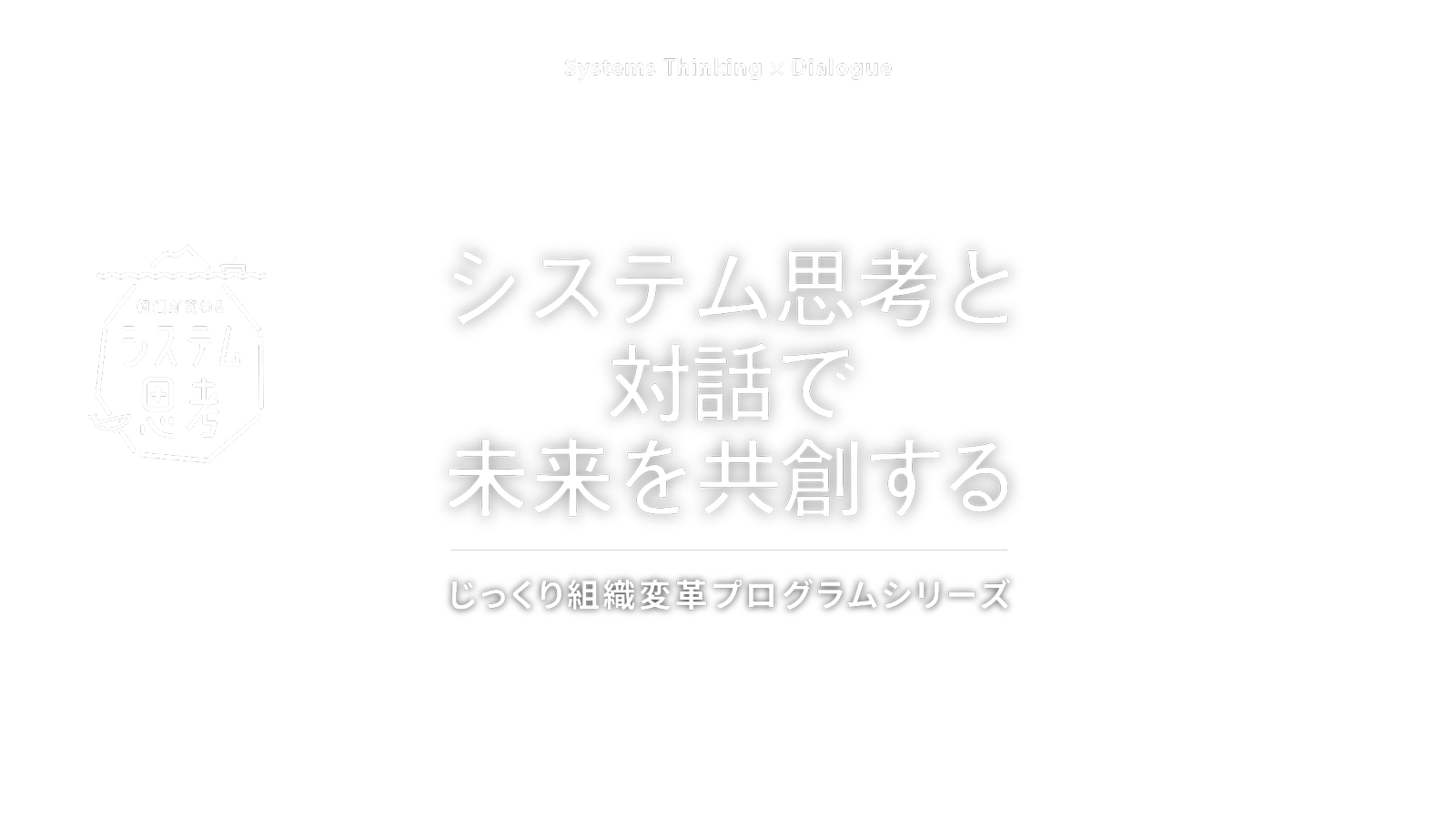
対話を重ね、構造やダイナミズム、価値観、バイアス等を丁寧に明らかにしながら、共に未来を創造する──。一般社団法人たまにのじっくり組織変革プログラムシリーズは、複雑で正解のない時代にこそ威力を発揮する、組織変革のアプローチです。
プログラム概要
システム思考の体験・実践から、ソリューション共創力向上まで。いずれのプログラムにおいても、対話を重ね、大きなシステムの構造やダイナミズム、根底に流れる価値観やバイアスを明らかにしながら、自らを知り学び合うことを通じて、望む未来を共に創造する場と技術とをじっくりと養います。
まずは体験を
システム思考
体験プログラム
体験的エクササイズを通じてシステム思考の基本概念を体験的に学びます。氷山モデルや因果ループ図による分析の基本的な流れを学び、複雑な課題を構造的に捉えるアプローチを体験します。
期間
1〜2日間
主な内容
システム思考体験ゲーム(2日間の場合)、 システム思考概要、因果ループ図による課題分析体験
こんな方に
おすすめ
期間
4〜8ヶ月(隔週実施)
主な内容
システム原型、因果ループ図による課題分析、介入策検討、メンタルモデルの理解と対話の実践
こんな方に
おすすめ
本格的な習得を目指す
システム思考入門/
実践プログラム
システム思考を体系的に理解し、実際の組織課題に適用する実践力を身につけます。入門と実践の2段階構成で、対話力向上も重視したプログラムです。
イノベーションを促す
ソリューション共創
プログラム
システム思考とデザイン思考を融合した「たまに流ソリューション創出プロセス」で、本質的な変化を自らリードし新規事業や革新的ソリューションを創出する次世代のリーダーを育成します。
期間
6ヶ月〜2年
主な内容
システム思考概要、因果分析実践、メンタルモデルの理解と対話の実践、ソリューション創造の6つのプロセス、課題分析、評価軸設定、リサーチ、アイデア創出、プロトタイプテスト、検証
こんな方に
おすすめ
各プログラムは独立して受講可能ですが、段階的に学習いただくことでより深い理解と実践力が身につきます。
導入企業の声
インタビュー術のワークショップもお願いしましたが、こちらも素晴らしいものでした。”たまに”のみなさんのお人柄もあって、終始リラックスした雰囲気で学ぶことができたのもありがたかったです。

ANSビジネスプランニング統括部
ANS人材開発グループ
兼 ANSサプライチェーン統括部
計画グループ

専務取締役
社内でも、曖昧だった情報を図や文章に落とし込んでコミュニケーションを取るケースや、前提を確認し合う機会が増えてきました。システム思考を使って課題解決に取り組む動きも出始めており、今後の変化が楽しみです。
たまにさんは、システム思考への深い理解を持つだけでなく、複雑な状況でも長期的な視点で笑顔を絶やさず伴走してくださいます。その穏やかな姿勢に支えられながら一緒に仕事をすることがとても心地よく、信頼して長くお付き合いできるパートナーです。
社長として何よりうれしいのは、彼らの“目の色”が少しずつ変わり、主体的に動く姿が増えていること。成果が目に見える形になるのはこれからですが、現場の空気や会話の質に、すでに変化の兆しが表れているのを感じています。
“たまに”さんは、参加者への伴走だけでなく、社内のコミュニケーションへの配慮も細やかで、フェーズ毎のレポートも実に丁寧で充実しています。これまでにない本格的な人材育成プログラムですが、社長として、安心して若手の応援と環境整備にエネルギーを注ぐことができています。

代表取締役社長
ファシリテーターのご紹介
北海道大学農学部卒。慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科修士課程修了(学位授与正代表)。大学在学中に2年間休学し、1年間フランスに滞在後、西欧・東欧・北アフリカ・中東・インド等15カ国を旅する。卒業後、出版社ディスカヴァー・トゥエンティワンで編集に従事。
英ケンブリッジ大学客員研究員(2019)、慶應義塾大学殿町先端研究教育連携スクエア特任助教(2021-22)、現慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科(SDM)特任助教。
地域において人びとが健やかに生きるための「つながり」をどう育み醸成するかという問いを軸に、人々がより健やかでいられる社会環境に寄与する仕組みの研究と実践をしている。主な領域は、互恵性とシステム思考とシステムズエンジニアリング。関心領域は、アートと旅と食べることと食べないこと、大好きな人たちとゆるくおだやかな時を紡ぐこと。
研究実績:
学会発表、学術論文掲載:
ウェルビーイングを陽に考慮したシステムデザイン方法論 — 第2報:地域のウェルビーイングの計測指標の提案及び有効性検証 —(2025)(原著論文/共著)
Concept Verification and Validation Using Psychological Scales through an “Eating-Together” System Enhancing Connectivity for Busy-Generation Urbanites with Neighborhood Community in Japan (2022)(学会発表/単著)
修士論文:「都市に住む多忙世代が参加しやすい 近隣住民「一緒に食事」システムの提案」(2020)
資格:
Associate Systems Engineering Professional (INCOSE)
米国PMI認定プロジェクトマネジメントプロフェッショナル
EAP(Employee Assistance Program)コンサルタント
2003年東京海上日動システムズ株式会社入社。システムエンジニアとして勤務する傍ら、同社の未来思考で課題を解決する場「フューチャーセンター」を運営するチームに参加する。これをきっかけに、自由でフラットな対話を通じて未来をつくることの大切さと可能性に気づき、社内外のステークホルダーを巻き込んだ対話の場を各所で持つ。
また、ワークショップ設計やファシリテーションのスキルを活かしたグラフィックレコーディングを独学で身につけ、さまざまなプロジェクトで実施。
現在はフリーランスとして「どうすれば体温の高いコミュニティをつくることができるか?」をテーマに、ファシリテーターやグラフィックレコーダーとして活動中(屋号:リトルフルーツ)。NPO法人bondplace理事、慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科(SDM)特任助教。
趣味はフラメンコを踊ること、歌舞伎や宝塚を始めとしたお芝居を観ること、旅行先で冒険すること、着物と茶道とお昼寝。
研究実績:
修士論文「コミュニティの活性度を可視化し向上させるための手法の提案」(2019)(優秀賞)
学術論文掲載:
論文題目: Proposal of a Method to Evaluate and Promote a Degree of Community Activation
掲載論文誌: Review of Integrative Business and Economics Research, Vol. 8(s3), 1-19.
著者: Kaoruko Manabe, Nobuyuki Kobayashi, SeikoShirasaka, Makoto Ioki
資格:
米国PMI認定プロジェクトマネジメントプロフェッショナル
早稲田大学商学部卒。慶應義塾大学システムデザイン・マネジメント研究科修士課程修了。2006年より日本テレビ放送網株式会社にてアナウンサーとして勤務。主に報道、スポーツの生放送を担当し、五輪、箱根駅伝、東日本大震災、英国ロイヤルウェディングなども取材・中継した。退社後、フリーランスとしてテレビ・ラジオ・各種媒体で活動中。
インタビューや対話への第三者的な介入を通して、人が持つ魅力や可能性、暗黙知を引き出すことに喜びを感じる。また、自身も子育て当事者であることから、子育てをめぐる社会や地域の環境、母親たちの困りごとの改善に関心が高い。
NPO法人ミラツク非常勤研究員。音楽、旅行、香りを楽しむことが好き。(アロマテラピー検定1級)
研究実績:修士論文「つながりを形成するきっかけとしての自己開示と類似性の認知促進ツールの提案」(2022)。同題目にて、日本創造学会にて提案構築過程を発表。
代表メッセージ
日々相互依存度が高まり、
複雑で予測困難になっていく時代に。
世界は今、ますます複雑化し予測困難になり続けています。
組織が直面する問題の多くも、同様ではないでしょうか。
こうした複雑な状況においては、高い能力を誇るリーダーや専門家も、「正解」を持ちえるものではありません。
「治療が病気よりも手に負えないこともある」。
これは、システム思考を学ぶ者にはよく知られたシステムの特性のひとつです。
改善策や解決策として「治療」を行うことが、長期的に見れば次の「症状」を生み出して、
実際には事態を深刻化させているケースが少なくないというのです。
こうした事態を打開する強力な術となるのが、「システム思考」と「対話」です。
私たちが提供する「じっくり組織変革プログラムシリーズ」は、
「システム思考」と「対話」を柱に、問題を生む構造を可視化し認識や価値観を共有することを通じて相互理解を促し、
個々人が発揮できる力を高め、複雑な問題を越えた未来の組織の共創を促します。
変革にはスピードが求められますが、価値観や考え方、行動様式の変容が求められるものだけに、焦りは禁物です。
プログラムには実践的な学びと対話をバランスよく組み込み、
思わず笑いがこぼれるような楽しいエクササイズや、自分や組織と向き合う時間も重ねながら、
思考様式や行動の変容をじわじわと促していきます。
それぞれの「いいこと」が、組織にとって、そして、未来を生きるすべての人々にとっての「いいこと」であるために──。
みなさまと手を携え、おひとりおひとりと向き合いながら、精一杯お手伝いいたします。
一般社団法人たまに
代表理事




